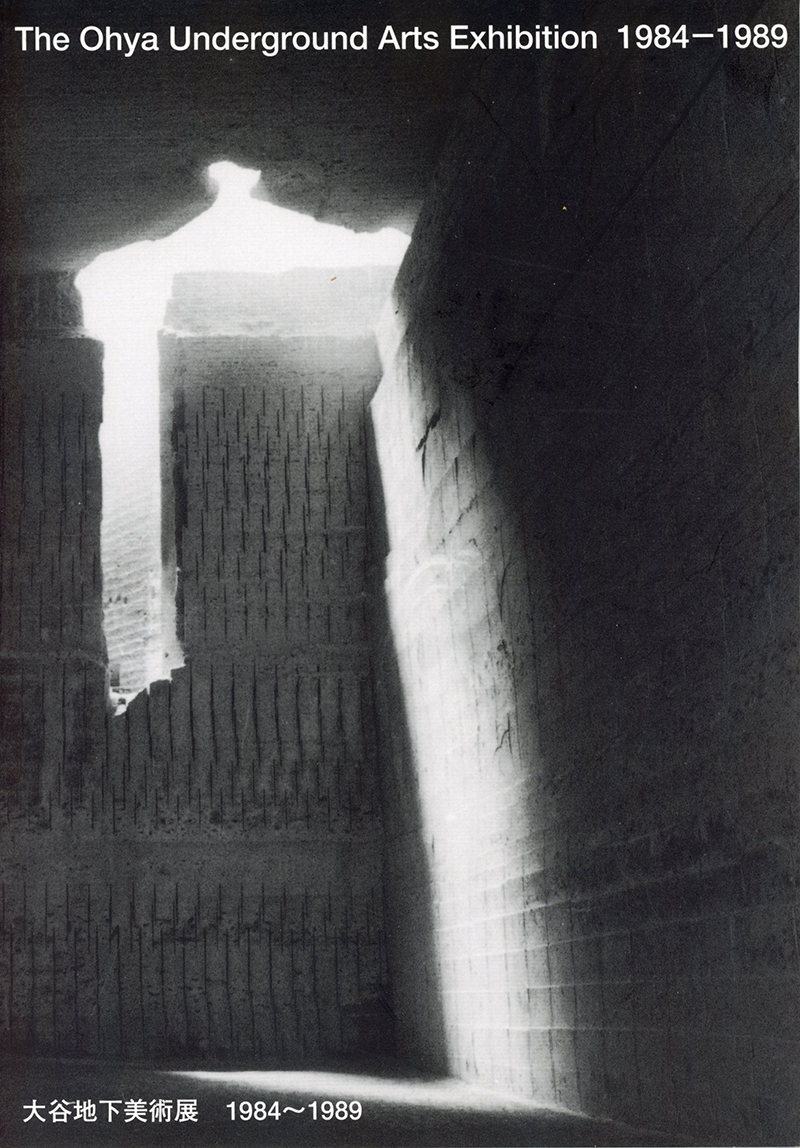text01_06
『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収いま考えてみると、サブタイトルの中の《ダブル・バインド※注》という語は、この第6回展を取り巻いていた状況を、実に良く言い表わしていたと思う。そして、私自身にとっても、このネーミングがまさに“でき過ぎ”と思えるほどの印象が残されているのだ──。
■ 当時の私自身と周辺状況
地下採掘場跡(以下─『あそこ』)は、私に向けて、表現への欲望を沸き立たせるエネルギーを圧倒的な力で流し込んできた。それは私の中で、「面白い事ができる」という、ほとんど何の根拠もない強い幻想と動機づけとなった。しかし一方で、「何もしない状態が一番いいかもしれない」という、裏腹な思いも同時に侵入してきた。まるで、まっ白なキャンバスの前で筆を持ちながら、逡巡し、葛藤する画家のように、強烈な二つ磁場の渦中に私は宙吊りにされた。
また、私個人の表現上の問題意識の中には、〈場〉と〈素材〉の持つ力に、余りにも頼り過ぎるインスタレーションへの懐疑と嫌悪が、当時、大きく頭をもたげていた。〈場の異化作用〉という名目のもと、単にディスプレイ的に「作り上げてしまう」だけのインスタレーションとは別の方法論を、私は標榜していた。しかし、『あそこ』からは、その単なる〈場の異化作用〉へと私を誘惑し、安住させてしまうかもしれない怪しい気配を感じ、妙な戸惑いを覚えていた。
それらはどういうことかというと、『あそこ』自体が、あまりにも日常空間と隔たった特殊な〈場〉であるがゆえに、個人の〈内部〉を揺さぶる不思議な力を秘めながらも、逆に、あっという間に、社会のしくみ・制度という〈外部〉の文脈の中に組み込まれてしまう危うさも抱え込んでいることを意味した。つまり、『あそこ』は我々作家や関係者にとって、様々な欲望が触発され、実験精神が試される所であると共に、意識の持ち方によっては、ただの「もう一つの変わった美術館」に、いとも簡単に成り果ててしまう、両刃の剣のような所でもあったのだ。
その頃私は、格好良く言うと、さり気なく人の意識に変化を起こしたり、世界の認識について再編成を目論むような表現を、美術と自分の〈生〉のトータルな関わりの中で志向していきたいと思っていた。単に画廊や美術館を用いた〈場の異化作用〉を目指したり、個人の世界観を露出するだけではとても済まされないものを感じていた。そう、あれは1989年。20世紀後半の歴史に残る激動の年だったのだ。ベルリンの壁は崩壊し、共産主義という人工的な虚妄の理想世界は消えつつあった。日本では長い〈昭和〉が終りを告げたが、まだ資本主義のただれきった爛熟の真只中でバブル経済に浮かれていた。文化産業の商品化も加速度的に推し進められていた。それこそ現実の中で、世界観の見直しと再編成が進行していた。そんな状況の中、必然的に、私自身の美術そのものに対する考え方や活動も、いろいろな意味で再検討を迫られていたのだ。そして、その具体的な試みの一つのモデルケースとして、「何かできるかもしれない」という漠然とした思いとともに、私は自分にとって二回目の大谷地下美術展に、やや迷いながら臨んでいったのだ。