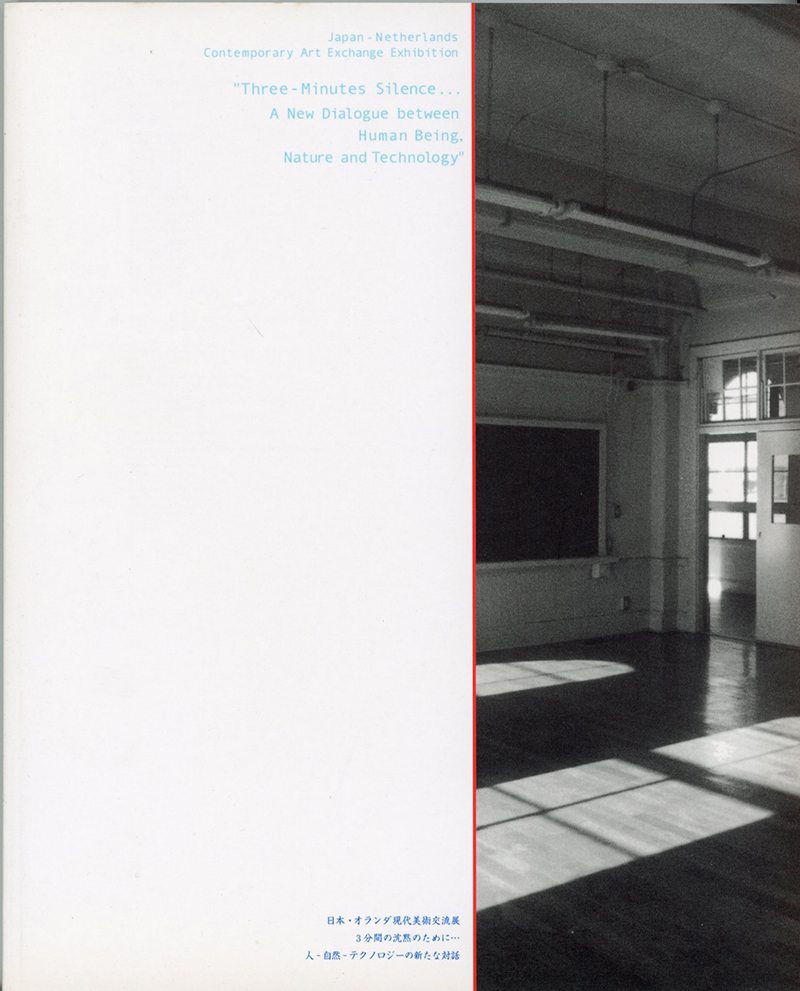text05_11
『3分間の沈黙のために…:人─自然─テクノロジーの新たな対話』カタログ(2002) 所収■希望の場へ
作品と場、あるいは身体性と場の関係について多くの議論がなされている。場が主題となるのは現在の社会空間の広がりと無縁ではない。ないしは作品の多様性が新しい場を求めはじめたのかもしれない。
50年代のハプニングやその後のアース・ワークやエンバイラメントな展開を経験したひとびと、そして作家と批評はそこに明らかに新しさという名の歴史への批判性が内在していることをみいだす。『パフォーマンス』の著者、ゴールドヴァーグがそうした現象を〈異議申し立て〉としたのは、形式の新しさや陳腐さも乗りこえたところにある批判性であったのは確かである。場の問題はそれが単に空間を意味していたのではなく、場そのものがもたらすアウラや固有性が作品と結びつくと考えられたからである。いつでも神話のスタートは単純である。巨大な絵画を描くポップ・アーティストにとってロフトは必要不可欠か、もしくはその逆に、ロフトが生みだす絵画かという問いであった。にもかかわらず巨大さはそれまでの絵画の領分を拡大し、やがて視覚と網膜性という新たな概念を生みだす。そのような例は枚挙にいとまがない。
単純さは偶然を生みだし、やがて論理が生まれる。演繹的にはベンヤミンが再び登場し、マクルーハンに論旨の帰結を与える。すなわち、〈場〉の問題が独占的な美学から学際的になったことを意味する。勿論わたしたちは古典を否定する必要はない。古典からみれば現在の〈場〉を包括する創造的手段は冒険主義である。現象的には刺激、興奮、スキャンダリズムが渦巻き、手法的には反復、拡大、偶然、複合、倒錯が主題となる。最も特徴的なのは仮構と消耗が平然とまかり通ることである。しかし、それは流行ではなく、確実に表現の本質にせまるものだという点で古典への決別を表わすことである。本来、作品はどのような立場であれ、素材であれ、極めて消耗的なものではないか、という問いである。もともと芸術は社会的存在として冒険主義的に登場したのではないか。という再びの問いである。
考えてみるとこの現象は実に都市構造と似ていることに気がつく。収奪と放棄によるくりかえし。それらを受けとめながら生々流転する日常の生活。反動としての疑似自然論としての環境問題へのアプローチ。すなわち、わたしは芸術がすでに様々な社会的役目を終えたのではないか、と自問する。
そのような彼方からひと握りのオルガナイザーが現われようとしている。彼等が問いかけるのは芸術の社会的役目ではない。問いかけるのは自律性によってのみ生みだされる人間の生きる場への興味である。パドゥルズを育て、今また十思スクエアに希望をたくす酒井信一がその一人である。そのあなたの立っている〈場〉こそ最初の芸術の生まれる場であると指す人である。彼と共に歩む一歩を共有した時間であった十思スクエアが未来の〈場〉になることを希望する。